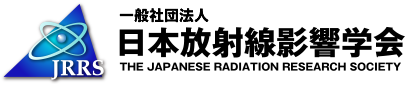p.53の調節機構の新展開
| 論文標題 | Regulation of p53 activity through lysine methylation. |
|---|---|
| 著者 | Chuikov S, Kurash JK, Wilson JR, Xiao B, Justin N, Ivanov GS, McKinney K, Tempst P, Prives C, Gamblin SJ, Barlev NA, Reinberg D. |
| 雑誌名・巻・ ページ・発行年 |
Nature, 432, 353-360, 2005. |
| キーワード | p53 , メチル化 , 翻訳後修飾 , DNA損傷 , ATM |
このグループは長年、世界の転写、クロマチン研究をリードしていることで有名である。数年前、histone H3のLys4をメチル化する酵素Set9を同定した。ところが、Set9は単独ではヌクレオソーム構造中のhistone をメチル化できず、また、生体内では他のhistone lysine methyltransferase (HKMT)、Set1、Ash1、SMYD3などがhistone H3のLys4のメチル化に関わっていることが明らかになってきた。そこで、著者らがSet9の新規基質を探索したところ、その一つとしてp53が見つかった。p53の部分断片、点変異体を用いた検討から、メチル化部位はLys372であることを割り出した。このリジンはC末端付近のいわゆる調節領域に存在し、近くにはリン酸化、アセチル化、ユビキチン化、SUMO化など他の翻訳後修飾部位が密集している。また、Set9をメチル化状態のp53ペプチド、副産物のS-adenosyl L-homocysteine共存下で結晶化し、構造を解析した結果も示している。
次に、Lys372メチル化状態特異的抗体を作製し、細胞内でのメチル化状態を検討した。293F細胞やU2OS細胞においてp53のLys372は確かにメチル化を受けており、また、その程度はアドリアマイシン処理によって上昇した。触媒部位に変異を加えたSet9やsiRNAを添加すると減少したことから、Set9が主要なp53 Lys372メチル化酵素であると考えられる。また、p53を増減させると、それに伴って標的遺伝子p21、Bax、Hdm2などの転写が変化した。これに相関してアポトーシス細胞の割合の変化も見られた。更に、35SメチオニンラベルによってSet9がクロマチン中のp53を安定化すること、クロマチン免疫沈降(ChIP)によってメチル化されたp53がin vivoでp21などのプロモータ領域に結合していることを示した。これらの結果から、Set9がアポトーシスにおける(おそらく細胞周期チェックポイントにおいても)p53の働きを増強していると考えられる。
1990年代後半、リン酸化状態特異的抗体を用いた研究が一気に加速したが、p53はその火付け役の一つであった。1997年にはp53のアセチル化が発見され、今回は更にメチル化修飾の存在が示された。このようなp53の複雑、多彩な翻訳後修飾は、この分子が細胞内外のさまざまな情報の「ハブ」であることを改めて感じさせる。また、p53はその高い注目度により、今やタンパク質の翻訳後修飾研究、あるいはもっと広範なタンパク質研究の「ハブ」となったと言っても過言ではないだろう。
関連論文1<C末端領域の新たな機能:p53 linear diffusion along DNA requires its C terminus> McKinney, K, et al. Mol. Cell 16, 413-424 (2004)
p53は大雑把に言って、N末端の転写活性化領域、中央部の配列特異的DNA結合領域(コア)、C末端のオリゴマー形成領域に分けられる。C末端領域はこの他、配列特異的DNA結合を「負に」制御する領域と考えられている。これにはいくつかの根拠がある。i)この部分を削るとDNA結合が促進される。ii)この部分にエピトープを有する抗体添加によってDNA結合が促進される。iii)C末端領域の多くの部位のリン酸化、アセチル化などによってDNA結合が促進される。i)は明解だが、ii)、iii)については、一般的には脱抑制の結果と解釈されている。ところが、数こそ少ないものの、「否、C末端部位はDNA結合を逆に促進するのだ」という報告もある。著者らは最近、p53のC末端領域が環状のDNAに対する結合を促進するという報告をしている。一見矛盾する結果の原因が何かは分からないが、実験条件の中で決定的に異なるのはDNAの長さや状態(ヌクレオソーム構造をとっているかどうか)である、と指摘している。こういった内容から、C末端negative regulatory domain説に真っ向から勝負しようという気焔が感じられる。
ここで提起されるもう一つの問題は、p53がいかにして標的配列を見つけだすか、ということである。「3次元」空間の中で飛び回って直接標的配列を見つけるのか、それとも、まずDNAに結合してしかる後に「1次元」空間を歩き回って標的配列を見つけるのか。これは配列特異的DNA結合タンパク質には普遍的な問題であるが、後者の重要性が示されている例として、大腸菌のlac repressorやEcoRVなどを引き合いに出している。Introductionからして大変味わい深い論文である。
p53が「1次元」空間の中で拡散するかどうかをどうやって評価するか。この方法がまた面白い。いわゆるゲルシフトの変法で、2001年にDNAポリメラーゼの補助因子の研究で用いられた手法らしいが、概略次の通りである。まず、5'末端を放射性ラベル、3'末端をビオチンラベルした2本鎖DNA(66bp)を用意し、p53を結合させる(prebind)。その後に大過剰(400倍)の非標識DNAを加える(chase)。もし、p53が66bp以上動き回れば、最初に結合した標識DNAから「滑り落ち」、後から加えた非標識DNAの方へ結合してゲルシフトのシグナルが減少する。しかし、p53を結合させた後、ストレプトアビジンを加えれば末端のビオチンに結合することにより、p53が滑り落ちにくくなるだろうー何やら漫画みたいな話だが、実際やってみるとそうなる。もちろん、3'末端をビオチン標識していなければ、こういうことは起こらない。
さて、ここで問題のC末端領域を削ってみると、ストレプトアビジンの効果がなくなる。また、C末端領域単独の場合、全長p53の場合より強い効果が見られた。このことから、p53は実際にDNA上を行ったり来たりすることができ、それにはC末端領域が必要であると結論する。また、著者らが以前報告した環状DNAについてchaseの効果を調べてみると、ビオチン化DNAにストレプトアビジンを加えた場合とほとんど同様であった。当然、環状DNAに端はないので、p53がこの上を動いても滑り落ちることがないと考えると、うまく説明できるではないか。次に、C末端のリン酸化、アセチル化の影響を調べたが、通常の短いDNAを用いた場合の結果と異なり、結合能の変化は認められなかった。そこで、著者らは改めてp53の機能におけるC末端領域の役割を問い直す。C末端を削ったp53をH1299に発現させた場合、全長を発現させた場合に比べて、p21、hdm2など標的遺伝子への結合やその発現誘導が低下することをクロマチン免疫沈降(ChIP)やレポーターアッセイなどで示している。著者らは、p53のC末端領域は「負の調節」領域なんかではない、標的配列への結合や転写活性化に重要である、と訴える。
方法も面白く、説得力も十分である。しかし、そこで筆者に疑問が生じた。ここでは、「p53が一旦標的配列に結合した後の動き」を見ているではないか。「まずとにかくDNAに結合してから標的配列を探す」というのとは違うのではないか、と。しかし、そのことについてもdiscussionで一応きちんと触れられていた。p53の標的遺伝子のプロモータ領域にはしばしば複数の標的配列がある。そこで、1個目を見つけて結合し、そこから動くことによって近隣の他の標的配列を探すのではないか。複数の標的配列の1つが必要なもので他は単なる「目印」なのか、それともお互いが協調的に転写活性化に関わるのか分からないが、これはこれでまた面白い考え方である。著者らは3次元的探索を否定してはいない。むしろ、3次元と1次元の両方の探索法を組み合わせることで、より効率良い標的遺伝子誘導を起こすのであろうと述べている。
p53のC末端が負の調節領域であるという論文が相次いで有名誌に発表されたのは1990年代前半のことである。それから、10年以上たった今、この問題が再燃しそうである。もしかすると、「大逆転」が起こるかも知れない。
関連論文2<翻訳関連分子のもう一つの顔:The haploinsufficient tumor suppressor p18 upregulates p53 via interaction with ATM/ATR. >Park, B.-J, et al. Cell 120, 209-221 (2005)
著者らは長らく翻訳に関わるアミノアシルtRNA合成酵素の研究を行ってきた。この酵素は数個の補助因子(p43, p38, p18)とともに複合体を形成する。この研究は、p18変異マウスを作製するところから始まる。ホモの欠損マウスはE8.5までにほとんどが死亡し、生まれてこなかった。ヘテロの欠損マウスもメンデル比の半分程度で、残りは誕生までに死亡していると考えられたが、生まれてきたマウスには目立った異常は見られなかった。ところが、特に15週齢以降、高頻度でがんを発症した。リンパ腫が最も多かったが、乳癌、精巣癌、肉腫、肺癌、肝臓癌など多種類のがんが見られ、うち一部は多重がんであった。これらのことから、p18がさまざまな臓器、組織のがんに関わる強力ながん抑制遺伝子である可能性が考えられた。
そこで、p18+/-マウスの脾臓、胸腺、線維芽細胞などを取り出してみると、正常マウスの細胞と比して増殖が盛んであった。また、p18の発現量や局在は細胞周期によって変化し、S期に最も多く、核内に移動してフォーカス状に分布した。更に、p18はDNA傷害(ここではアドリアマイシンと紫外線)によって誘導され、p18+/-細胞はアドリアマイシン誘導アポトーシスに対する抵抗性を示した。これらのことから、p53が細胞周期やアポト?シス調節に関わっている可能性が示唆された。
多種類のがんに対する抑制作用、細胞周期、アポトーシスの調節?これらはp53と共通する。そこで、著者らはp18とp53の関係を探った。p18+/-細胞ではp18とともにp53の発現量の低下が見られた。また、ヒト大腸癌細胞HCT116(注1)にp18を過剰発現させるとp53量の増加やp21の誘導に伴って、増殖抑制が認められた。一方、p53あるいはp21を欠損させたHCT116細胞では、p18による増殖抑制が認められなかった。また、アンチセンスでHCT116細胞のp18発現を低下させると紫外線によるp53の蓄積誘導やアポトーシス関連分子PUMAの発現誘導が抑制された。これらのことから、p18がp53を介して細胞周期進行抑制やアポト?シス誘導を引き起こしていると考えられた。
では、いかにしてp18はp53に作用するか。AT(ataxia-telangiectasia、毛細血管拡張性運動失調症)患者由来細胞を用いた検討から、p18による細胞増殖抑制とアポト?シス誘導にはATMが必要であることが明らかになった。次に、免疫沈降実験によって、p18がATM、ATRと結合していること、そして、その結合がDNA損傷(アドリアマイシン、紫外線)によって増強されることが分かった。更に、p18過剰発現によりATMのSer1981の自己リン酸化(注2)が上昇し、逆に、p18+/-細胞やp18アンチセンス導入細胞においてはアドリアマイシン処理によるATM Ser1981のリン酸化誘導が低減することから、p18がATMの活性化に関わっている可能性が示唆された。以上の結果を総合することにより、p18→ATM/ATR→p53→p21, PUMAなど→細胞増殖抑制、アポトーシスという経路の存在が浮かび上がった。
最後に、著者らは種々のヒトがんにおいてp18の発現低下が認められることを示している。また、p18が存在する6p24-25はリンパ腫で頻繁にLOHが見られる領域である。興味深いことにp18の発現低下は主として正常なp53を有する細胞で認められ、p18あるいはp53のまた、p18発現が低下したがんでは、p21の発現低下も見られた。これらのことは、p18がp53と同一経路でがんを抑制するという上記の仮説を支持する。