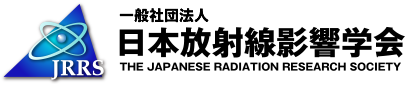前立腺がん幹細胞を標的とするα線治療
| 論文標題 | Targeting Prostate Cancer Stem Cells with Alpha-Particle Thrapy |
|---|---|
| 著者 | Ceder J and Elgqvist J |
| 雑誌名・巻・ ページ・発行年 |
Front Oncol. 6:273, 2017 |
| キーワード | α線 , RI内用療法 , 前立腺がん , がん幹細胞 |
この論文はがん幹細胞 (CSCs)に対して標的α線治療 (Targeted Alpha Therapy:TAT)を選択すると、転移がん患者の生存期間を延ばし、従来よりも完治の期待が高まる可能性について主張している。去勢抵抗性前立腺がん(CRPC)は今日では完治が難しい病気であり、前立腺がん細胞の大部分をターゲットにする新しい薬剤が開発されたにも関わらず、進行すると生存期間が短くなる。効率的なラジオアイソトープ(RI)内用療法で腫瘍再発の根源を標的とすることは、今日の標準的な治療法と比べて生存期間を延ばすことが期待される。著者らは様々な前立腺CSCsマーカーを標的とする新しいα線内用療法が近い将来、転移前立腺がんの治療を変えると考えている。今回紹介した論文が、α線内用療法の理解を深めると共に、CSCsを標的とした革新的な治療法開発のヒントになれば幸いである。
がんの標的治療における放射性薬剤の発展は、抗体-薬物複合体の腫瘍特異的な輸送や、原発がんと播種がんの診断や治療を可能にした。古典的な標的治療では腫瘍全般で高発現し、周囲の組織では低発現の抗原を標的としていた。しかし、これらの治療法でがんが完治しないのは、がん細胞のうち放射線治療など既存の治療法に対して抵抗性であるサブ集団細胞が存在するためであり、さらに放射線抵抗性細胞は大部分の細胞とは異なる抗原を示すためであることがわかってきた。これらの細胞はしばしばCSCsと呼ばれる。CSCsは自己複製や分裂の過程で、腫瘍に存在するあらゆるタイプの細胞になる能力をもつがん細胞である。もしCSCsが根絶されなければ、腫瘍は治療後に再発するおそれがある。外部照射と内用療法いずれの放射線治療においても、放射線抵抗性の一因となるCSCsをいかに効率よく制御するかが重要な課題となっている。
放射線の一つであるα線は細胞を通過する際、細胞膜、細胞質および核に重篤なダメージを与える。非常に修復しにくいとされるDNA二重鎖切断はそのダメージの一つである。そのため、α線はわずか数回通過する程度で、CSCsのように既存の治療法に抵抗性を持つ細胞を殺傷することが可能である。この論文は、前立腺がんの治療法におけるα線放出核種の利用の可能性を検討し、前立腺癌に対するTATの適応の是非を考慮する際のパラメーターについて論述している。
前立腺がんは男性におけるがん死亡の上位にあり、局所的な前立腺がんは手術によって治すことができ、転移した場合はアンドロゲン除去療法が治療の第一選択となり、90%以上の患者に効果的である。しかし、アンドロゲン除去療法による抗腫瘍や緩和は腫瘍がCRPCになるまでの18-24ヶ月間しか効果を示さない。転移CRPCに対する治療法は最近までほとんどなかったが、近年はアンドロゲン合成阻害剤アビラテロン、アンドロゲン受容体拮抗薬エンザルタミド、タキサン骨格カバジタキセルを用いた化学療法、シプロイセルTを用いた免疫療法や塩化ラジウム223 (ゾフィーゴ®)による活性型骨細胞の標的治療などの新たな治療法が多数開発された。このような治療法の急増により転移CRPCをもつ男性患者の生存率は向上したが、根治には至らず前立腺がんは未だに不治の病である。しかしながら、がんの再発はCSCsによってもたらされるので、これを根絶させることで、アンドロゲン除去・抑制療法など既存の治療法では治せない前立腺がん患者でも完治もしくは寿命を延長させることができるかもしれない。
かつてα線はその物理的特徴から臨床利用は難しいと考えられていたが、近年はRI内用療法への応用が注目されている。α線放出RI内用療法薬ゾフィーゴ®(塩化ラジウム-223)が2013年に世界で初めて欧米で承認されたのをきっかけに、α線を用いたRI内用療法の研究が欧米を中心に盛んに行われている。日本では、法的規制等によりα線研究は限られていたが、2008年より国内臨床利用に関する検討が開始され、臨床試験を経て2016年に日本国内でもゾフィーゴ®が保険適用された。従来のRI内用療法で主にβ線を利用してきたが、α線はこれよりも局所に高エネルギーを付与できることから、これまで放射線抵抗性であったがん種に対しても効果が期待されている。
TATは腫瘍抗原に特異的に結合する分子にα線放出核種を標識した放射性薬剤を用い、β線放出核種を用いた従来の放射免疫療法と区別されている。α線は2個の陽子と2個の中性子を持ち、組織内で放出されると3-6個の細胞(60-90μm)内に全てのエネルギーを放出する。その飛程の短さは微小がん、さらには単腫瘍細胞をもターゲットすることを可能とし、とくに非標的正常組織への被ばくの低減に有用である。TATによく用いられるα線放出核種はアクチニウム225(Ac-225)、ラジウム223(Ra-223)、ビスマス213(Bi-213)、ビスマス212(Bi-212)、そしてアスタチン211(At-211)の5つである。Ac-225は壊変途中で4回α線を放出し、At-211およびその娘核種のキャリアー分子への安定的結合や迅速な内在化が可能となれば、高い治療効果が望める。223Raは壊変途中で4回α線、2回β線を放出し、すでに上記で述べたように、塩化ラジウム223の形で前立腺がんの骨転移治療に用いられている。Bi-213は壊変途中で1回α線を放出し、Ac-225 /Bi-213ジェネレーターより生成することができる。Bi-212は壊変途中にα線とβ線を1回ずつ放出し、娘核種Tl-208から高エネルギー(2.6MeV)のγ線が放出されるため、投与された患者はRIが減衰するまで必ず遮蔽病室での滞在が必要である。At-211はPb-207に至るまでの2つの壊変経路でいずれも1回α線を放出する。この核種の化学的性質はヨウ素に似ている。TATにとても有用であるが、サイクロトロンを用いた製造が必要であるため、供給が限られている。
高LETであるα線の殺傷効果はβ線に比べて高く、酸素濃度や細胞周期の影響を受けにくい。高殺傷効果のα線はTATに利用されることもあり、これまでいくつかの臨床試験が行われてきたが、早期臨床試験を完了したものは限られている。いくつか例を挙げれば、Bi-213やAt-211を用いた再発脳腫瘍に対するTATや、卵巣がん患者に対するAt-211を用いた腹腔投与によるTAT、骨髄性白血病に対するBi-213やAc-225を用いたTAT、B細胞非ホジキンリンパ腫に対するBi-213標識抗CD19/抗CD20抗体を用いたTATや、転移性メラノーマに対するBi-213を用いたTATは早期臨床試験の完了に至っておらず、FDAに承認されているのは唯一塩化ラジウム223の前立腺がん骨転移に対するTATのみである。
飛程が非常に短く、組織内で高LETのα線の線量評価は、非常にチャレンジングな取り組みである。α線によって各細胞核に与えられるエネルギーの統計的変動が大きくなると、平均吸収線量が低く見積もられるからである。そこで、マイクロドジメトリーの応用が必要となってくる。KellererやChemelevskyらも1975年に発表した論文で、局所線量の偏差が20%を超えるとき、特定のターゲットへの付与されるエネルギーの確率的ばらつき、つまりマイクロドジメトリーは必ず取り入れるべきと述べている。MIRD Pamphlet No.22ではα線の放射線生物や線量評価について包括的に言及しており、他の観点からα線の線量評価におけるマイクロドジメトリーの応用の必要性について言及したレビューや論文も報告されている。