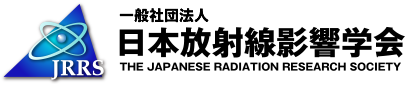クロマチンリモデリング因子CHD1のN末端のモチーフはDNA損傷シグナルの初期応答に必要である
| 論文標題 | Human CHD1 is required for early DNA-damage signaling and is uniquely regulated by its N terminus |
|---|---|
| 著者 | Zhou J, Li J, Serafim RB, Ketchum S, Ferreira CG, Liu JC, Coe KA, Prrice BD, Yusufzai T |
| 雑誌名・巻・ ページ・発行年 |
Nucleic Acids Res., 46(8): 3891–3905, 2018 |
| キーワード | CHD1 , CHD2 , DNA損傷修復 , CtIP , γH2AX |
【はじめに】
クロモドメイン-ヘリカーゼ-DNA結合遺伝子1(CHD1)は、脊椎動物の発生に必須なクロマチンリモデリング因子であり、成人の前立腺癌との関係性も指摘されている。クロモドメインを持つタンパク質CHDは酵母ではChd1pの一種類しか発現していないが、脊椎動物ではCHD1-9の9種類が発現している。これまでの幾つかの研究からCHD1は遺伝子の転写発現制御に関与することが知られているが、細胞内における挙動や役割に関しては不明な点が多い。DNA損傷剤を用いた感受性解析からCHD1は二本鎖切断(DNA double strand breaks: DSB)修復に関与する可能性が示唆されていたほか、PTEN(癌抑制遺伝子)を欠損した前立腺癌や乳がんにおいてCHD1の阻害は合成致死(転写やDNA修復など細胞の生存に関わる機能に関連する相補的な遺伝子の組み合わせにおいて、両方が働かないと細胞が死滅すること)を誘導できることが報告されていた[1]。本論文では、DSB修復に CHD1がいかに関与しているかを、ヒト培養細胞系を用いて解析した結果、CHD1は相同組換え(Homologous Recombination: HR)を介したDSBの効率的な修復に必要であることを発見している。また、CHD1のN末端領域を、細胞における生化学的活性および修復機能を調節する新規自己阻害ドメインとして同定している。本論文でのCHD1の機能解析は放射線により生じたDSBに修復機構の理解においても有益であるので本稿で紹介したい。
【ヒトCHD1は相同組換えを介したDSBの効率的な修復に重要である】
CHD1とDNA修復との関係を理解するために、CHD1の存在下または非存在下で、2つの主要なDSB修復経路である相同組換え(Homologous Recombination: HR)修復および非相同末端結合(Non-Homologous End Joining: NHEJ)修復の効率を測定した。この分析のために、筆者らはヒト骨肉腫細胞株U2OSを用いて確立された緑色蛍光タンパク質による解析の結果、CHD1ノックダウン細胞とコントロールを比較して、HR効率が50%以上低下することが観察されたが、NHEJ効率に有意な差異を見出さなかった。この結果から、CHD1はHRによる修復経路に関係することがわかった。
そこで筆者らは、CHD1をノックアウトしたヒト網膜色素上皮細胞RPE1のPARP阻害剤Olaparib (HR関連因子であるBRCA1/BRCA2遺伝子と合成致死を調べる)とPTEN (既往の研究においてCHD1と共にクロマチンリモデリングに必須であることが報告されている1) 阻害剤VO-OHpicに対する感受性を計測した。その結果、コントロール細胞と比較してCHD1ノックアウト細胞はPARP阻害剤とPTEN阻害剤の両方に高い感受性を示した。この結果から、CHD1はPARPとPTENの両者と合成致死
である可能性がある。
次に筆者らは、CHD1がどのようにHRを促進するかを理解するために、CHD1がCtIP(DSBs部分に集合し、DNA末端の切除に関わるヌクレアーゼ)集合に重要であるか調べた。この分析のために、筆者らは、RPE1細胞のWT(wild type)とCHD1ノックアウト細胞にレーザー照射し、レーザー跡に集まるCtIPを免疫蛍光染色で確認した。その結果、WTにおいては約45%のレーザー跡にCtIPの集合が確認できたのに対し、CHD1ノックアウト細胞においては20%未満のCtIPの集合であった。また筆者らは、上記と同じ条件の細胞に2Gy照射し、免疫蛍光染色によってCtIPの集積の数を観察した。その結果、CHD1ノックアウト細胞のCtIPの集積の数がWTと比較して少ないことがわかった。さらに筆者らは、WTおよびCHD1ノックアウト細胞における放射線照射後のリン酸化H2AX(γH2AX:損傷箇所を修復するタンパクに知らせる役割)のレベルを測定した。その結果、CHD1ノックアウト細胞におけるγH2AXのレベルがWT細胞よりも低いことを見出した。これらの結果から、CHD1はCtIPの集合に関与し、初期のHR過程に重要な役割を果たすことがわかった。
【CHD1のDNA結合、ATPase活性、リモデリング活性、クロマチン構造形成がN末端によって大きく抑制される】
CHD1の欠損がDNA修復に欠陥をもたらすという上記の実験結果から、CHD1は他のクロマチンモデリング因子とは異なり、リモデリング活性とDNA修復両者への関与が示唆された。とりわけ、同じCHDファミリーのクロモドメイン-ヘリカーゼ-DNA結合遺伝子2(CHD2)はCHD1と約67%の塩基配列同一性を示しているが、CHD1のようなDNA修復に関わる機能は保持していない。そこでCHD1配列とCHD2配列を比べたところ、CHD1のN末端が独特な配列をしていることが判明した。そこで筆者らは、CHD1のN末端配列が特有の役割を保持していると仮定して、N末端配列の役割を特定する実験を行なった。
筆者らはまず、CHDファミリーが持つDNA結合特性とCHD1のN末端の関係性を調べるために、N末端欠損CHD1(CHD1 ΔN)、N末端+クロモドメイン(CD)欠損CHD1(CHD1 ΔN+ΔCD)、CD欠損CHD1(CHD1-iΔCD)、CHD2のCDを入れ替えたCHD1(CHD1-swap CHD2 CDs)、CHD2のDNA結合ドメイン(DBD)を入れ替えたCHD1(CHD1-swap CHD2 DBD)を作り出し、DNAとの結合強度を測定する実験をおこなった。その結果、CHD1 ΔNはDNAとの結合強度が増加し、CHD1 ΔN+ΔCDでは更に結合強度が増加、それ以外の条件ではWTと比較して特に変化はなかった。この結果から、CHD1のN末端はDNA結合を抑制する機能を有することが示唆された。
次に筆者らは、CHD1のN末端が自身のATPase(ATP: エネルギーの放出・貯蔵、あるいは物質の代謝・合成の役割)活性へどう関与がするのかを調べるために、WT、ΔN、ΔN+ΔCDの3条件のCHD1を作製し、それぞれの条件に対しATP+プラスミドDNA、ATP+プラスミドクロマチンをそれぞれ培養し、加水分解されたATPの量を測定した。その結果、CHD1 ΔNではCHD1 WTと比較してプラスミド、クロマチン両者で加水分解量が増加し、CHD1 ΔN+ΔCDでは更に増加することがわかった。この結果から、CHD1のN末端とCDは自身のATPase活性を抑制する機能を有することが示唆された。
さらに筆者らは、CHD1のN末端が自身のクロマチンリモデリング活性に関与するのかを調べるため、REA(Restriction Enzyme Accessility)assayを行なった。具体的には、15個の制限酵素(外来のDNAを切断してそれを持つものの動きを制限するもの)HaeⅢ認識配列を持ったクロマチン、ATPとCHD1(またはその変異体)を含む溶液を培養し、その後のクロマチン断片のサイズを調べた。その結果、CHD1 ΔNでは、CHD1 WTと比較して、リモデリング活性が増加することで、クロマチン構造の変化が起き制限酵素による切断頻度が増加することがわかった。この結果から、CHD1のN末端がリモデリング活性を抑制する機能を有することが示唆された。
次に筆者らは、CHD1のN末端がクロマチン構造形成に関係するのか調べるため、ヌクレオソーム形成試験を行った。方法としては、コアヒストンタンパク質、ヒストンシャペロンNAP-1、プラスミドDNA、ATP、TopoⅠとCHD1(またはその変異体)を含む溶液を培養し、その後のDNAサイズをアガロースゲル電気泳動によって確認することで、DNA構造の違いを調べた。その結果、CHD1 WTと比較してCHD1 ΔNはDNAバンドの低下、つまりプラスミドDNAがスーパーコイル状へと構造変化することがわかった。この結果から、CHD1のN末端はクロマチン構造の形成を抑制する機能を有することが示唆された。
次にCHD1のN末端(271個のアミノ酸で構成)のどの部分がCHD1自身の活性を抑制しているか調べるために、CHD1のN末端の最初から69個(Δ69)、137個(Δ137)、209個(Δ209)、そして271個(ΔN)全てを欠損させたCHD1を作り出した。次に、WT CHD1とそれら欠損させたCHD1のATPアーゼ活性を比較するため、ATPアーゼ アッセイ行なった。実験手法は前述した通りである。その結果、ATPase assayでは、WT CHD1と比較して、Δ69 CHD1とΔ137 CHD1のATPase活性が僅かに増加し、Δ209 CHD1は更にATPase活性が増加し、ΔN CHD1でATPase活性が最大となった。次に筆者らはN末端を欠損させたCHD1とWT CHD1のクロマチンリモデリング活性の違いを調べるため、REA assayをおこなった。その結果、N末端の欠損部分が増加するにつれ、段階的にリモデリング活性が増加している事がわかった。
最後に、CHD1のN末端がCHD1自身の活性を抑制することを細胞内で確かめるため、RPE1細胞のWT、CHD1ノックアウトRPE1細胞にFull-length CHD1を遺伝子導入したもの、CHD1ノックアウトRPE1細胞にΔN CHD1を遺伝子導入したものをそれぞれ用意し、放射線照射した際のγH2AX のレベルを計測することでWT CHD1とΔN CHD1のDNA修復の活性を比較した。その結果、WTと比較して、Full-length CHD1を遺伝子導入したCHD1ノックアウト細胞、ΔN CHD1を遺伝子導入したCHD1ノックアウト細胞のγH2AXレベルが保持される傾向にある事がわかった。また、同様にWT CHD1とΔN CHD1のDNA修復活性の違いを調べるために、レーザー照射によってDNA損傷を引き起こし、その損傷部位に集まるCtIPを定量化する実験を行った。その結果、WTと比較して、Full-length CHD1を遺伝子導入したCHD1ノックアウト細胞、ΔN CHD1を遺伝子導入したCHD1ノックアウト細胞において、DNA損傷部位に集積するCtIPが保持されている事がわかった。これらの結果から、WT CHD1と比較してΔN CHD1はDNA損傷修復をより回復させる傾向が確認できた。これらの発見により、CHD1のN末端は、CHD1のDNA修復活性に必要とされず、ヒト細胞においてCHD1を抑制するような役割を果たす事が実証された。
【おわりに】
本論文では、CHDファミリーの1つで、クロマチンリモデリング因子であるCHD1が、HRを介したDSBの効率的な修復に関与することがわかった。さらに、CHD1の持つDNA結合、ATPアーゼ活性、クロマチンリモデリング活性、クロマチン構造形成機能は、自身のN末端によって大きく抑制されることが明らかになった。また、CHD1はPARPとPTENの両者と合成致死である可能性が示唆され、この結果は、がん治療の新たな発展に寄与する可能性を秘めている。今後の研究の進展に期待したいと思う。
【参考文献】
[1] Zhao,D., Lu,X., Wang,G., Lan,Z., Liao,W., Li,J., Liang,X., Chen,J.R., Shah,S., Shang,X. et al.(2017) Synthetic essentiality of chromatin remodeling factor CHD1 in PTEN-deficient cancer. Nature,542,483-488