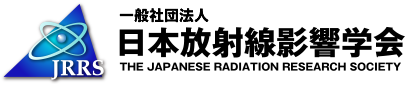ホウ素中性子免疫療法(B-NIT)による免疫療法抵抗性の克服とアブスコパル効果の誘導
| 論文標題 | Overcoming immunotherapy resistance and inducing abscopal effects with boron neutron immunotherapy (B- NIT) |
|---|---|
| 著者 | Fujimoto T, Yamasaki O, Kanehira N, Matsushita H, Sakurai Y, Kenmotsu N, Mizuta R, Kondo N, Takata T, Kitamatsu M, Igawa K, Fujimura A, Otani Y, Shirakawa M, Shigeyasu K, Teraishi F, Togashi Y, Suzuki M, Fujiwara T, Michiue H |
| 雑誌名・巻・ ページ・発行年 |
Cancer Sci, 115(10): 3231-3247, 2024 |
| キーワード | abscopal effect , advanced melanoma , boron neutron capture therapy , boron-neutron immunotherapy , immune combination therapy |
【背景・目的】
免疫チェックポイント阻害剤(ICIs)は免疫チェックポイントと呼ばれる特定の分子をブロックし、がん細胞が免疫細胞に認識されやすくすることで、がん細胞が免疫システムから逃れることを防ぎ、免疫によりがん細胞を攻撃する治療法である。ICIsは多くの進行性悪性腫瘍に対して有効であるが、免疫療法に反応しない患者の克服が課題である。一方、BNCT(Boron Neutron Capture Therapy)はがんに選択的に集積するホウ素薬剤を投与し、中性子線を照射することでがん細胞のみが反応を起こす局所化学放射線療法である。BNCTではBPAといったホウ素を含むアミノ酸代謝の高い様々な悪性腫瘍の細胞に取り込む薬剤を使用している。本研究では、放射線抵抗性および免疫療法抵抗性の進行期悪性黒色腫マウスモデルを用いて、BNCTとICIsを組み合わせたホウ素中性子免疫療法(B-NIT)による効果について、局所腫瘍への効果だけでなく遠隔部位にも及ぶ免疫反応(アブスコパル効果)を確認することを目的とした。
【結果】
1. BPA(4-Borono-L-phenylalanine)の体内動態
B16F10マウス黒色腫細胞を用いた進行黒色腫マウスモデルでBPAの薬物動態を評価した。皮下投与により右脚部腫瘍(局所)で約50 ppm、左頸部腫瘍(遠隔)で12.7 ppm、腹腔内投与により局所腫瘍で約30 ppm、遠隔腫瘍で15.1 ppmの腫瘍内ホウ素(B-10)濃度を確認した。また、局所腫瘍におけるB-10の腫瘍/正常組織比(T/N ratio)は腹腔内投与よりも皮下投与群で高く、投与後1時間で腫瘍/皮膚=3.7、腫瘍/筋肉=2.8、腫瘍/血液=3.9を示し、BNCTにおける治療適応の基準である2.5を上回った。
2. B-NITの腫瘍抑制効果
B16F10マウス悪性黒色腫細胞をC57BL/6Jマウス右脚部と左頸部に移植し、4, 7, 10, 13日目に抗PD-1抗体を投与し、8日目に右脚部のがんに対して中性子線照射を行った(KURRI, 5 MW, 12分)。この際、左頸部のがんは、フッ化リチウム板により中性子線を遮蔽した。BNCT単独群では局所腫瘍の増殖抑制効果は確認されたが、遠隔部位腫瘍には影響がなかった。ICIs単独群では局所腫瘍及び遠隔部位腫瘍の増殖抑制効果は確認されなかった。B-NIT群では局所腫瘍の増殖抑制効果に加え、遠隔部位腫瘍の増殖抑制効果(アブスコパル効果)が確認された。
3. B-NITの免疫細胞動態〜腫瘍浸潤性リンパ球TILs(Tumor-Infiltrating Lymphocytes)
細胞傷害性T細胞であるCD8(+)T細胞は、BNCT群では局所腫瘍でのみ集積が見られ、B-NIT群では局所及び遠隔主要局所腫瘍で集積が確認された。さらに、脾臓CD8(+)T細胞の増加は、BNCT群とB-NIT群の両方で観察され、B-NIT群でより顕著な増加を示した。また、B-NITにより効果記憶T細胞(CD44(+),CD62L(-)及びTEMs)の割合が局所及び遠隔部位で大幅に増加し、特に遠隔部位では早期活性化T細胞(CD8(+),CD69(+))も増加した。
4. 損傷関連分子パターンDAMPs(Damage-Associated Molecular Patterns)の誘導
免疫原生細胞死のマーカであるHMGB1(High Mobility Group Box 1)の血清中濃度が、BNCT群及びB-NIT群で有意に上昇した。特に、B-NIT群での上昇が顕著であり、腫瘍抗原の拡散や免疫系の活性化が示唆された。
5. B-NITにおけるCD8(+)T細胞性免疫効果
細胞障害性T細胞(CTL)の効果とCD8(+)T細胞の抗腫瘍効果の相関を確認するため、抗CD8(+)mAbを投与した。CD8(+)T細胞を枯渇させたマウスでは、B-NITの腫瘍抑制効果が失われ、特に遠隔部位でのアブスコパル効果の消失が顕著だった。この結果から。B-NITによるアブスコパル効果が、CD8(+)T細胞依存的であることが確認された。
【考察・まとめ】
B-NITは、BNCTによる腫瘍破壊がDAMPsの誘導を通じて腫瘍抗原を拡散させ、ICIsによる免疫応答活性化を促進することで、免疫療法抵抗性を克服できることを示した。特に、遠隔部位への抗腫瘍免疫効果(アブスコパル効果)は、これまでの放射線治療とICIsの組み合わせでは限定的であった点を大きく上回る成果である。また、本研究はB-NITが進行性黒色腫だけでなく、免疫療法抵抗性を示す他のがんにも適用可能であることを示唆している。BNCTが放射線源の制約により適用施設が限られている一方、適切な装置の普及や臨床試験の進展が期待される。今後の課題としては、臨床試験を通じた有効性の確認と、副作用の評価が必要である。また、他の免疫療法や薬剤との組み合わせによる治療効果の最適化を検討することが求められる。