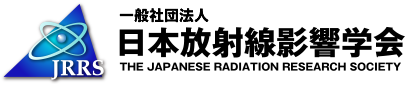頻繁な全身CTスキャンによる放射線は全身の免疫抑制と腫瘍組織の免疫活性化を引き起こす
| 論文標題 | Radiation from frequent whole-body CT scans induces systemic immunosuppression and immune activation of tumor tissue |
|---|---|
| 著者 | Dong J, Fu C, Li M, Wang Z, Li B |
| 雑誌名・巻・ ページ・発行年 |
Transl Oncol, 54: 102326, 2025 |
| キーワード | CT検査 , 腫瘍免疫 , インターフェロン , DAMPs |
【背景・目的】
本研究は、全身CT検査(CTスキャン)後にがん患者の血中インターフェロン(IFN)-βおよびIFN-γレベルが低下し、抗腫瘍免疫が弱まる可能性があるという臨床観察に着想を得て実施された。CT検査は腫瘍患者の診断や治療モニタリングに不可欠な画像診断技術であるが、X線による電離放射線が免疫系に及ぼす影響は十分に解明されていない。
先行研究では、低線量放射線が腫瘍免疫に二面的な作用を持つことが報告されている。すなわち、全身的には免疫細胞損傷による免疫抑制を引き起こす一方で、腫瘍局所ではM1型マクロファージへの分極促進、NK細胞やT細胞の活性化、制御性T細胞(Tregs)の減少を通じて免疫微小環境を改善する。しかし、全身免疫と腫瘍局所免疫の双方に対する影響を同時に検討した研究は存在しなかった。
そこで本研究では、複数回の全身CTスキャンが全身免疫、腫瘍免疫、および腫瘍制御に及ぼす影響を解明することを目的とした。
【方法】
Lewis肺癌(LLC)マウスモデルが用いられた。6週齢の雌C57BL/6マウスの左後肢皮下に1×10^6個のLLC細胞が移植され、腫瘍径が約4 mmに達して腫瘍が生着した時点で、マウスが無作為に対照群と全身CTスキャン群に割り付けられた(各群n=7)。腫瘍径が約6 mmに達した時点で、全身CTスキャン群には実際の医療用CT装置を用いて腹部CTの臨床プロトコル(120 kV、30–250 mAs、回転時間0.5–0.75秒)による全身照射が隔日で計5回行われた。腫瘍径の測定を行わない一部のマウスは、最後のCTスキャンから24時間後に血液、腫瘍組織および脾臓が採取され、ELISA、フローサイトメトリー、免疫組織学的解析、RNAシーケンス、単一細胞解析などが実施された。並行して、臨床的検証として造影CTスキャンを受けた腫瘍患者16名(年齢45〜76歳、男性7名、女性9名)から血液が採取された。これらの患者はいずれも頭部・胸部・腹部・骨盤を対象とする造影CTスキャンを受けており、治療経過の評価を目的に撮影が行われた。採血はCT撮影前および撮影24時間後に実施され、血清中のIFN-βおよびIFN-γがELISA法により定量された。
【主な結果】
1. ヒト患者における免疫機能への影響
造影CTスキャンを受けた腫瘍患者において、CTスキャンが免疫系に与える即時的影響が評価された。CTスキャン24時間後の血清解析の結果、抗腫瘍免疫の中心的メディエーターであるインターフェロン(IFN)-βおよびIFN-γが有意に低下し、一時的な免疫機能低下が確認された。この所見は解析が行われた全ての症例で共通して認められた。
2. マウスモデルにおける腫瘍増殖への影響
複数回の全身CTスキャンは腫瘍増殖を促進しないことが示された。腫瘍体積測定の結果、むしろ全身CTスキャン群では対照群と比較して緩やかな増殖傾向が示された(13日目:NC群約1300 mm^3、WBCTSs群約1000 mm^3)。統計的有意差は認められなかったが、腫瘍制御が維持される可能性が示唆された。
3. 全身性免疫パラメータの変化
血中免疫細胞の変化:フローサイトメトリー解析により、血液中のT細胞集団に顕著な変化が認められた。CD3陽性T細胞全体が減少し、特にCD8陽性キラーT細胞の減少が顕著であることが示された。CD4陽性ヘルパーT細胞も同様に減少した。血清サイトカインでは、IFN-βおよびIFN-γが著明に低下し、全身性の免疫抑制状態が確認された。
脾臓における免疫細胞の変化:脾臓でも血中と同様の傾向が観察された。T細胞全体が減少し、特にCD8陽性キラーT細胞の割合が大幅に低下した。遺伝子発現解析では、IFN-γ産生を司るインターフェロンγ遺伝子(Ifng)発現が著しく低下し、NK受容体や細胞傷害活性に関連する遺伝子群の発現低下によって、免疫機能の抑制が分子レベルで確認された。
4. 腫瘍における局所免疫の活性化
一方、腫瘍組織ではIFN-βとIFN-γが顕著に上昇し、腫瘍組織へのCD8陽性キラーT細胞浸潤が著明に増加していることが明らかになった。これらの浸潤T細胞の多くが活性化マーカーを発現し、実際にIFN-γを産生する機能的な細胞であることが確認された。
また、免疫組織学的解析により、腫瘍組織内のCD8陽性細胞密度や、腫瘍細胞にアポトーシスを誘導する細胞傷害酵素グランザイムB産生細胞が増加していることが確認された。遺伝子発現解析では、NK受容体、グランザイム、共刺激受容体など腫瘍殺傷関連遺伝子群が上方制御されており、腫瘍内T細胞が一時的ではなく持続的な抗腫瘍応答能を獲得したことが示唆された。
さらに単一細胞解析により、マクロファージのケモカイン分泌によるT細胞誘導、樹状細胞の抗原提示による活性化、NK細胞のIFN-γ産生の増強が協調的に作用し、腫瘍内で複雑な細胞間相互作用ネットワークの形成が確認されていることが明らかになった。この免疫活性化カスケードは、放射線損傷を受けた腫瘍細胞から放出された損傷関連分子パターン(DAMPs)を起点として段階的に進行し、単独では達成できない強力な抗腫瘍応答を実現していることが示された。
【考察】
観察された「全身免疫抑制と腫瘍局所免疫活性化の逆説」は、放射線損傷により腫瘍細胞から放出されるDAMPsが局所免疫応答を増幅することで説明された。放射線は免疫細胞を抑制する一方で、より高感受性を持つ腫瘍細胞が強く損傷されDAMPsを放出し、その結果マクロファージや樹状細胞が活性化され、続いてCD8陽性キラーT細胞の強力な抗腫瘍応答が引き起こされると考えられた。
また、線量が低すぎればDAMPs放出が不十分で免疫活性化が起こらず、高すぎれば全身性免疫抑制が優位となる閾値が存在する可能性が述べられている。この知見は、腫瘍タイプや個体差を考慮した個別化CTモニタリング戦略の必要性を示唆している。
【まとめ】
本研究により、頻回の全身CTスキャンが全身性免疫抑制と腫瘍局所免疫活性化という逆説的応答を引き起こし、腫瘍進行を促進しないことが明らかにされた。DAMPsを介した腫瘍局所免疫活性化が全身性免疫抑制を上回る可能性が示された。臨床的意義として、腫瘍の種類や患者状態に応じた検査頻度の最適化の必要性が示唆された。ただし、本研究は腫瘍を有するマウスで得られた結果であり、健常者・健康個体や通常の診断CTにおける応答については今後の検証が求められる。