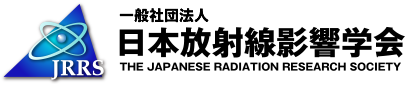ヒストンH1の脱アミド化がDNA修復の為のクロマチン弛緩を促進する
| 論文標題 | Histone H1 deamidation facilitates chromatin relaxation for DNA repair |
|---|---|
| 著者 | Tian Y, Feng T, Zhang J, Meng Q, Zhan W, Tang M, Liu C, Li M, Tao W, Shu Y, Zhang Y, Chen F, Takeda S, Zhu Q, Lu X, Zhu WG |
| 雑誌名・巻・ ページ・発行年 |
Nature, 641: 779–787, 2025 |
| キーワード | DNA二本鎖切断修復 , ヒストンH1 , 脱アミド化 , クロマチン , アセチル化 |
【背景・目的】
DNA二本鎖切断(DSB)は、放射線によって引き起こされる最も致命的なDNA損傷であり、放射線治療の効果と正常組織への影響は、細胞がDSBをどれだけ効率的に修復できるかに依存している。DSBが生じると、一時的にクロマチンが弛緩し、DNA修復因子が損傷部位にアクセスできるようになる。しかし、このクロマチン弛緩を引き起こす分子機構、とくにリンカーヒストンH1の翻訳後修飾(PTM)の役割は十分に理解されていなかった。本研究では、代謝酵素 CTP synthase 1(CTPS1) がDNA損傷に応答してヒストンH1の特定残基を酵素的に脱アミド化(deamidation)するという新たなPTMを発見した。この脱アミド化は、ヒストンアセチルトランスフェラーゼp300によるアセチル化反応が起こるための前段階として機能し、クロマチンを弛緩させてDNA修復を促進することが示された。さらに、CTPS1の高発現が放射線治療抵抗性と関連することも明らかにされた。これらの結果は、放射線が誘発するDNA損傷応答(DDR)におけるクロマチン構造制御の新たな仕組みを明らかにし、放射線感受性制御の新たな分子標的の可能性を示した。
【主な結果】
1. 各H1バリアントの中でH1.4が最もクロマチンを凝縮させることを確認
ヒトのH1ファミリーにはH1.1〜H1.4など複数のバリアントが存在する。著者らはまず、放射線(IR)照射後のヒストンH1の電荷変化を2次元電気泳動で解析し、複数のH1アイソフォーム(H1.2, H1.3, H1.4)が、いずれも正電荷の減少を示すことを確認した。次に、それぞれのH1をsiRNAでノックダウンした際のクロマチン弛緩度(高塩抽出法によるH3の溶出量)を比較したところ、H1.4のノックダウンで最も顕著なクロマチン弛緩が見られた。すなわち、H1.4は他のH1バリアントよりもクロマチンを強く凝縮させる機能を持つことが判明した。この結果と過去の報告を踏まえ、以降の実験ではH1.4を代表的バリアントとして解析を進めた。
2. CTPS1はH1を脱アミド化し、DNA損傷後に迅速にDSBへリクルートされる
質量分析の結果、ヒストンH1.4のアスパラギン残基(Asn)76および77が、CTPS1の触媒作用によりアスパラギン酸(Asp)へ変換される、すなわちアミド基(–CONH2)が脱離する「脱アミド化反応」が起こることを同定した(H1.4 N76D/N77D)。また、CTPS1は放射線照射やDSBを誘発する抗がん剤VP16処理後、数分以内にDSB部位へリクルートされた。さらに、in vitro 脱アミド化アッセイにおいても、酵素活性を保持する野生型CTPS1がH1の脱アミド化を誘導した。これらの結果は、CTPS1がDDRにおけるヒストンH1の酵素的脱アミド化酵素として機能することを示している。
3. H1.4の脱アミド化はp300をDSB部位へ誘導し、Lys75アセチル化を促進
ヒストンH1.4の脱アミド化を模倣する変異体(Asn76およびAsn77をAspに置換した H1.4-2ND)を用いた解析により、ヒストンアセチルトランスフェラーゼp300が脱アミド化型H1.4を優先的に基質として認識し、隣接するLys75残基のアセチル化(H1K75ac)を触媒することが明らかになった。一方、CTPS1欠損細胞や脱アミド化不能変異体(H1.4-2NA, H1.4-2NR)では、p300のDSB部位へのリクルートおよびH1K75ac誘導が著しく低下し、脱アミド化がアセチル化に先行する必須段階であることが示された。さらに、構造ドッキング解析でも、脱アミド化によってp300結合部位が立体的に近接し、相互作用が促進されることが示唆された。
4. H1脱アミド化はPARP1経路とは独立して作用
PARP1阻害や活性化条件下でも、H1(N76D/N77D)やH1K75acの形成には変化がなく、H1修飾経路とPARP1経路は独立したクロマチン弛緩機構であることが確認された。 PARP1が主にコアヒストンの構造をゆるめることでクロマチンを開くのに対し、H1修飾はリンカーDNAとの結合を弱めることでヌクレオソーム間の間隔を広げ、クロマチンをより開いた構造にすると考えられる。
5. 臨床検体でのCTPS1発現と放射線抵抗性の相関
子宮頸癌組織マイクロアレイ解析では、放射線治療前に採取された検体において、治療後に放射線抵抗性を示した患者群でCTPS1発現が上昇しており、CTPS1高発現群では全生存期間の短縮が確認された。さらに、放射線治療を受けた患者群の腫瘍検体では、CTPS1発現とH1脱アミド化レベルとの間に正の相関が認められた。また、マウス移植腫瘍モデルにおいても、CTPS1欠損腫瘍では放射線による増殖抑制効果が顕著であった。
【考察・まとめ】
本研究は、ヒストンH1がCTPS1による脱アミド化とp300によるアセチル化という二段階のエピジェネティック修飾カスケードを介して、放射線が誘発するDNA損傷後のクロマチン弛緩を制御することを初めて示した。特に、H1ファミリーの中で H1.4がクロマチン構造を最も強く規定する主要バリアントであり、その特異的な修飾が放射線誘発DNA修復における決定的役割を担うことを明確にした点は重要である。さらに、CTPS1高発現が放射線治療抵抗性と関連することから、CTPS1/H1修飾経路を標的とした放射線感受化療法が新たな治療戦略として期待される。また、本論文では解析の中心がヒストンH1.4に置かれており、他のH1バリアントを含めた総合的な役割については詳細な検討が行われていない。H1がDNA損傷修復以外にも多様な細胞機能に関与することを踏まえると、他のH1バリアントの修飾や機能的多様性を含めた包括的な解析が今後求められるだろう。なお、本論文ではノックアウト細胞に対してミュータントをアドバックする手法が随所に用いられているが、その際のクローナルなばらつき(clonal variation)に関する詳細な記述はなく、この点は結果の解釈上の留意事項といえる。